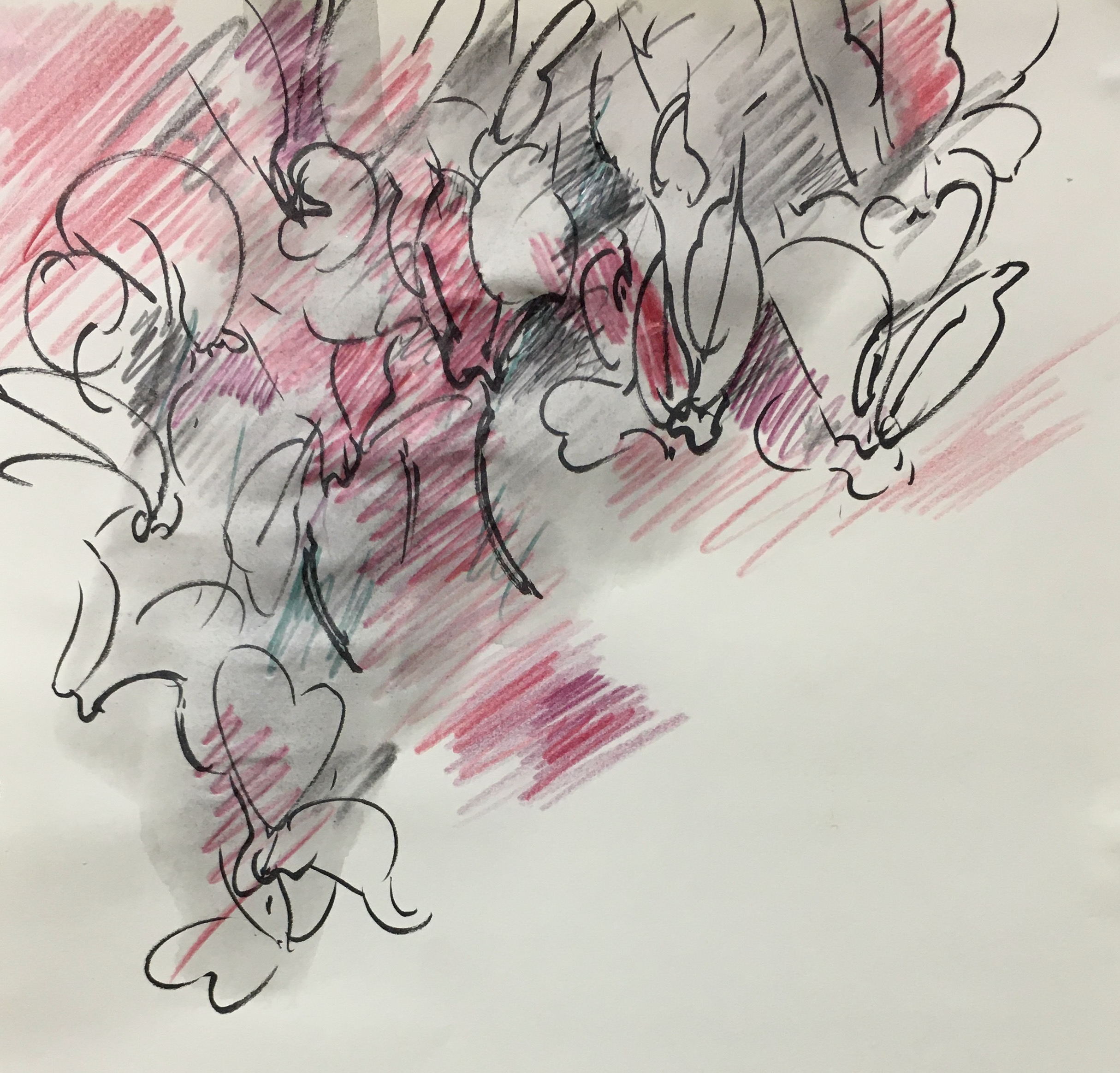0最近、寺田透の本を読んでいる。彼は1915年に生まれて、1995年に亡くなっている。私の父より少し若く、母よりも年長だ。
1
0大学生の頃、美術や文芸の評論を幾つか読んだ覚えがある。正統なことを言っているのだが、難渋で読むのに疲労したのを覚えている。途中からは避けていた。
ー再読をするきっかけになったのは、石井恭二の現代語訳「正法眼蔵」の注に引用されていた、禅の「偈」という詩型についての言及だった。この一文を書いた寺田と引用した石井の間に、ただならぬ空気を感じたからだ。
ーあらためて「絵画の周辺」を読み、彼の美術批評の凄さに驚いた。私が密かに紡いでいた日本美術史の解釈について、すでにいくつもの点を抑えて指摘しているのだった。これは画家でないとわからない視点と思っていただけに唸った。なぜ彼だけが気づいたのだろう。
ー
ー寺田は自分の評論の姿勢を書いている。絵画であろうと文芸であろうと、自分の存在を脅かすもの(作品)に拮抗する業だというのだ。したがって彼の文章は、論理を真っ直ぐに並べるようなことにはならない。身体の伴った思考のうねりが常に同居していて、いささかの偽りも許されないという姿勢がある。解らないところはそれを述べて、言い直すこともたびたびだ。それが晦渋の気味を醸し出す。そのことで、誰もが見えなかったものを見て、指摘する。並の評論家だったら、それらを己の手柄とするだろう。しかし、そのことに留意している気配がない。なぜだろう。
ー
ー私はいま、寺田の「道元の言語宇宙」を少しずつ読んでいる。この本の一部は岩波書店の公開講座で語られたものだ。聴衆は戦争を経験してきた同じ世代の人たちだろう。寺田は「眼蔵」を坐禅する人の思惟であると断言して、自分とは分離しながらもそれを読み解こうとする。ここにあるのは何だろうか。
ー
ー私には、一つ答えを導き出すことを求めていたとは思えない。存在のために、自分の目で見て感じ、考えることの覚悟をした人たちが居たのだと思う。
ー
ー今日は八月の十五日だ。覚悟を忘れないでいよう。
ー

8月の風景